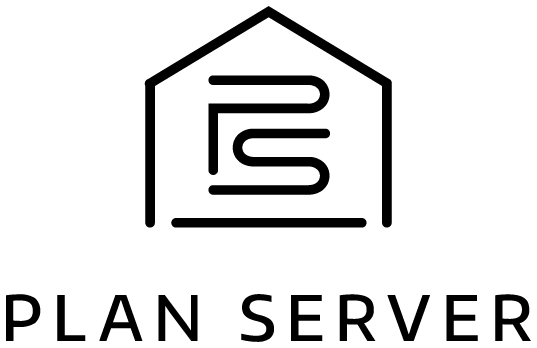COLUMN
コラム
住宅性能について(UA値 C値 Q値)
2025.09.17
住ごこち 家の性能
住宅性能を考えた時絶対に出てくる3つのワード
(UA値 Q値 C値)
専門的過ぎてなんだかわからないという方がほとんどです。
ここではこの3つの概要が掴めるように説明します。
まず(UA値 C値 Q値)は断熱の性能の数値と気密の性能の数値に分かれます。
断熱性能の数値が UA値 と Q値
気密の性能の数値が C値
UA値とQ値は計算して算出できるのですが、C値は実測しないと算出されません。
それぞれ何なのか。
「Q値(熱損失係数)」

「Q値(熱損失係数)」とは、
家の中の熱がどれくらい外に逃げにくいかを数値で示したものです。
建物の「外壁」「屋根(天井)」「床」などから失われる熱と、
換気によって失われる熱を合計し、延べ床面積で割ることで算出されます。
これは「室内と屋外の温度差を1℃とした場合、1時間あたりどの程度の熱が外へ出ていくか」を表しています。
Q値の数値が大きいほど熱は逃げやすく、
逆に小さいほど断熱性能が高く、冷暖房の効率も良くなり、
省エネ性の高い住まいであることを意味します。
Q値の詳しい内容はこちら
UA値(外皮平均熱貫流率)

「UA値(外皮平均熱貫流率)」とは、
建物からどのくらい熱が外へ逃げやすいかを示す指標です。
外壁・屋根(天井)・床などの部位から失われる熱量を合計し、
それを建物全体の外皮面積(外壁・屋根・床の合計面積)で割って算出します。
数値が大きいほど熱が逃げやすく、
逆に数値が小さいほど断熱性が高く、省エネルギー性能に優れた住まいであると評価できます。
Q値は建物全体の熱損失量を延べ床面積で割って求めるため、同じ断熱材を使って建てても建物の形状や規模によって数値が変わってしまいます。
例えば、外壁や屋根の面積が少ないシンプルな形の建物はQ値が小さくなりやすく、同じ形状であれば延べ床面積が大きいほどQ値は小さく算出されます。そのため、Q値だけでは本当の断熱性能や省エネ性能を正確に比較することができません。
一方でUA値は、熱損失量を「外皮面積(外壁・屋根・床などの合計)」で割って計算します。そのため、建物の形が複雑になっても、また延べ床面積が大きくなっても、数値のブレが少なく公平に性能を評価できます。
この理由から、平成25年の省エネ基準改正以降は、建物の断熱性能や省エネ性能を示す指標としてQ値ではなくUA値が採用されています。
C値(隙間相当面積)とは

C値は「隙間相当面積」を数値化した指標です。建物全体の隙間面積を床面積で割った値で表し、単位は「cm²/m²」となります。つまり「床面積1㎡あたりにどれくらいの隙間があるか」を示すものです。C値が小さいほど隙間が少なく、気密性が高いことを意味します。
住宅性能を示す数値には、ほかにもUA値(断熱性能)、Q値(熱損失係数)、ZEH基準などがありますが、C値は国の基準に含まれていません。
そのため、工務店やハウスメーカーによって重視度が異なるのが現状です。
しかし「気密性は意味がない」とは言えません。たとえば断熱性能(UA値)がどれだけ高くても、家に隙間が多ければ、冬は冷気が、夏は熱気が侵入しやすくなり、せっかくの断熱効果が十分に発揮されません。
イメージするなら、断熱材だけの家は前を開けた蓋を開けたクーラーボックスのようなもの。それだけでは外気の影響をうけてしまいます。
クーラーボックスはフタをしっかり占めて初めて効果が発揮されます。
家も同じで断熱と気密を組み合わせることで、本来の性能を最大限に引き出せると言えます。