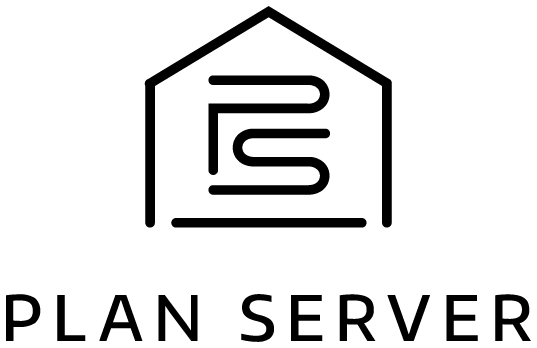COLUMN
コラム
住宅性能について(C値編)
2025.09.17
住ごこち 家の性能
家の快適性の指標の一つになるC値
住まいを選ぶ際に「快適さ」や「省エネ性能」を大切にしたいと考える方は多いでしょう。そこで注目すべき指標のひとつが、住宅の気密性を示す「C値(隙間相当面積)」です。C値を理解することで、夏は涼しく冬は暖かい、一年を通じて心地よく暮らせる住まいづくりが可能になります。
本記事では、C値の基本的な意味や算出方法、住宅性能への影響、そして快適な住環境との関わりについて詳しくご紹介します。これから家づくりを考えている方や、新しい住まい探しをしている方にとって役立つ内容となっていますので、ぜひご覧ください。
C値とは?

C値とは、住宅の「気密性」を示す数値です。気密性とは、建物に隙間が少なく、外気が室内に出入りしにくい状態を指します。
気密性の高い住まいは、窓・壁・床などにできる小さな隙間が少なく、外の空気と室内の空気が混ざりにくくなります。その結果、冷暖房効率が高まり、快適な環境を保ちやすくなります。
高気密住宅のメリット
- 換気計画が正確に設計できる
-
冷暖房の効率が良くなる
-
結露が起こりにくい
-
光熱費の削減
-
花粉やホコリなどの侵入を防ぎやすい
-
音漏れや騒音を軽減できる
隙間が少ない家は、まずは計画換気を計画的に実行するために絶対に必要です。義務図けられている24時間換気の換気計画でどこからどう空気を流してどう排出するのか。
家中に隙間があると計画外の通気が発生して計画通りに換気ができません。
また外気の侵入が抑えられるため室温が安定しやすく、冷暖房費の削減にもつながります。また、結露を防ぎやすいので、カビやダニの発生も抑えられ、健康面での安心感も高まります。さらに、外からの騒音を遮断しやすく、室内の音も外に漏れにくくなるため、快適性が増すのです。
C値(隙間相当面積)の意味と特徴
C値は「隙間相当面積」を数値化した指標です。建物全体の隙間面積を床面積で割った値で表し、単位は「cm²/m²」となります。つまり「床面積1㎡あたりにどれくらいの隙間があるか」を示すものです。C値が小さいほど隙間が少なく、気密性が高いことを意味します。
住宅性能を示す数値には、ほかにもUA値(断熱性能)、Q値(熱損失係数)、ZEH基準などがありますが、C値は国の基準に含まれていません。そのため、工務店やハウスメーカーによって重視度が異なるのが現状です。
しかし基準がないから「気密性は意味がない」とはいうことではありません。
省エネ基準が出来たとき最初はC値の基準がありましたが、いつの間にか基準がなくなりました。
おそらく、実測でしか計れないC値に基準を設けてしまうと、大手ハウスメーカー含めてクリアできない会社が多くなってしまうのが理由じゃないかと思います。
たとえば断熱性能(UA値)がどれだけ高くても、家に隙間が多ければ、冬は冷気が、夏は熱気が侵入しやすくなり、せっかくの断熱効果が十分に発揮されません。
イメージするなら、断熱材だけの家は「ざっくり編みのセーター」を着ているようなもの。暖かいけれど、隙間から熱が逃げてしまいます。そこに「ウィンドブレーカー」を羽織ることで暖かさを閉じ込められるのです。断熱と気密を組み合わせることで、本来の性能を最大限に引き出せると言えます。
C値の計算方法と例
C値は次の式で算出されます。
C値(cm²/m²)= 住宅全体の隙間面積の合計(cm²) ÷ 延床面積(m²)
-
(例1)延床132㎡(約40坪)でC値=1.0の場合
132㎡ × 1.0cm²/㎡ = 隙間面積132cm²(はがき1枚ほど) -
(例2)延床132㎡(約40坪)でC値=2.0の場合
132㎡ × 2.0cm²/㎡ = 隙間面積264cm²(はがき約1.8枚分)
同じ床面積でも、C値の違いで隙間の大きさに大きな差が出ることがわかります。測定は専門業者が「気密測定器」を用いて行い、必要に応じて隙間を補修して性能を改善します。
C値が住宅性能に与える影響
C値が小さい家は隙間が少なく、外気の影響を受けにくいため、気密性が高くなります。結果として次のような効果が期待できます。
-
結露の抑制と耐久性の向上
結露はカビやダニの原因になるだけでなく、木材の腐朽を招き、家の寿命を縮めます。気密性を高めることで、木材の含水率を抑え、構造の強度低下を防ぐことができます。 -
冷暖房効率の改善
C値が高い(隙間が多い)住宅では、冬に室温20℃を維持しても体感温度が17℃程度まで下がることがあります。一方、C値0.8程度の高気密住宅なら20℃を保ちやすく、快適性が大きく向上します。 -
建物の耐久性と健康面への効果
湿度コントロールがしやすくなり、シロアリ被害のリスク軽減やアレルギー対策にもつながります。
つまり、C値を改善することは単に「快適性」を高めるだけではなく、建物を長持ちさせ、家族の健康を守る大切な要素でもあるのです。
そしてこのC値は家を建ててからC値を上げるのはほぼ不可能です。
新築の時だからこそしっかりと気密性の高い建物にする必要があります。